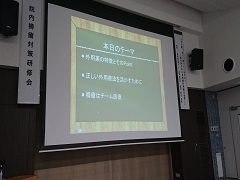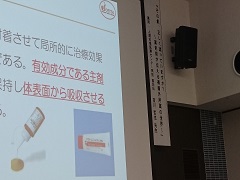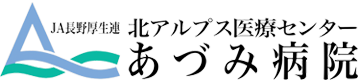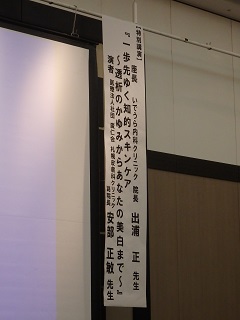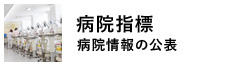WOCNブログ
外用療法は塗布量が大事!
今月上旬に、上越地域医療センター病院薬剤師の宮川さんをお招きして、
褥瘡管理対策研修を行いました。
テーマは、「その創、正しく塗っていますか?~薬剤師が伝える褥瘡外用療法の世界~」
講演依頼の際に「タイトルはまじめでないものにして欲しい」ことを伝えましたが、
そのようなリクエストや、看護師から講演依頼が来たのは初めてだったそうです。
ちょっと意外。。。
外用療法について、より専門的な立場の薬剤師さんに講演をお願いするのがベストと考え、その中でも褥瘡認定師でもある宮川さんが最適と判断しました。
外用薬のしくみ、軟膏基剤による分類、基剤の機能別特性、塗布量など外用療法についてや、チーム医療、NSTとの連携のことなども講演して頂き、学ぶことが多い内容でした。
塗布量については、日頃から指導が難しいと感じています。
褥瘡の状態や、薬袋の日付を見て「塗布量がきっと少ないと思う」とアセスメントして、適量がどれ位なのかを伝えます。
宮川さんは、「看護師間で塗布量に差があること」を学会でも発表していて、私も同じことを考えていました。
1日でも早く褥瘡を治癒させるために、滲出液の量や褥瘡の状態から、「適量」とはどれ位なのかアセスメントができるNsを増やしたいですね。
まずは、皮膚科医に相談してから。
先生方はきっと賛成してくれると思います。
いつもありがとうございます。 WOCN ふりはた
WOCNブログ
次年度のメンバー
28年度も残りわずかになってきました。
私は、褥瘡対策委員会、排尿ケアチーム、CSTの運営に関わっているので、毎年この時期は、「今度、褥瘡対策委員になりましたのでよろしくお願いします」とか「希望をしたのですが、他にも希望者がいてダメでした」とか「勉強がしたくて立候補したんです」などと、
声を掛けてくれるスタッフがいます。
院内にはたくさんの委員会やチーム、役割(チームリーダーやプリセプターナースなど)が存在し、通常の業務以外にも求められることが多いのが現状です。
認定看護師として組織横断的な活動をしていますが、それぞれの病棟に核となってくれるメンバーが存在しているおかげで、認定の活動ができるといっても過言ではありません。
それぞれが各部署で、リーダーシップを発揮し、チームとしての機能が向上するようサポートするのも重要な役目であり、後に続いてくれる人材を育てなければ。。。と考えている今日この頃なのです。
*諏訪大社の布橋、橋を歩くと違う世界に迷い込んだような感じでした。
いつもありがとうございます。 WOCN ふりはた
WOCNブログ
Gift(贈り物・才能)
先月、長野で開催されたセミナー「一歩先ゆく知的スキンケア~透析のかゆみからあなたの美白まで~」に参加しました。
血液透析に係わる医師やコメディカル向けのセミナーで、講師は安部先生です。
血液透析患者さんの痒みの発現には、複数の因子が関与していると考えられていますが、決定的な因子は特定されていません。
内服薬の効果もありますが、日頃のスキンケアも重要です。
先生も、ドライスキンの状態が続くと、痒みの神経が表皮まで伸びてくるために、少しの刺激で痒みが出現とすると講義されていました。
セミナーで1番印象に残っていたのは、先生がとても丁寧に深々とお辞儀をしていたこと。
(内容はいつでも最高なので。。。)
有料から無料、県内外のセミナーに参加し、多くのことを勉強させてもらっていますが、
「参加したことを後悔したり、反面教師にしよう。」と思うセミナーもたまにはあります。
今回は先生のお辞儀を見て「セミナーはGift!」と感じました。
贈る立場では、相手のことを想う気持ち(何が欲しいのかとか、喜んでもらいたいとか)が働き、貰う立場では、お金では買えない物をもらえるなんて、これ以上のGiftはありません。
そして、安部先生のスキルもGift(才能)なのだと思いました。。。
規模に関わらず、学習会全てがGiftだと考えると、私も更に真剣に考えないといけませんね。
*パーキングから撮影した諏訪湖。
いつもありがとうございます。 WOCN ふりはた
WOCNブログ
千里の道も一歩から!?
院内感染対策研修「尿道カテーテルの適応と抜去後のフォローについて」に参加しました。
身体状況と病態を十分に評価し、適切な尿路管理を選択することが望まれることや、
留置することの合併症として、尿路感染・膀胱結石・尿道皮膚ろうがあることなどの講義がありました。
先日参加した学会のワークショップで、カテーテル留置の理由として、
日常生活動作低下により離床が不良である・全身状態悪化を挙げるスタッフを散見するとの発表を聞き、どこも同じ状況なのだと感じました。
先進的に取り組んでいる病院だったので、殆どのスタッフは理解できていると思いますが、
周知徹底するには時間がかかるということがよく分かります。
カテーテル使用率が下がり、早期にカテーテルを抜去するという原則を徹底するために、間歇導尿管理の習得と、残尿測定のためのツールの整備が有効であったとのこと。
当院でも参考にさせて頂こうと思います。
カテーテルは早期に抜去する方が良いことや合併症については、看護師ならば誰でも理解できていることなのですが、医師の指示により留置している場合もあり、
簡単にはいきません。
カンファレンスで留置の必要性について取り上げられる日が来るように、
チームでしっかりと取り組みたい気持ちが強くなりました。
まずは、リンクナースの指導から。。。
「千里の道も一歩から」ですね。
*学会場のホテルで撮影。名古屋なので京都風(お内裏様が向って右側)ですね。
いつもありがとうございます。 WOCNふりはた