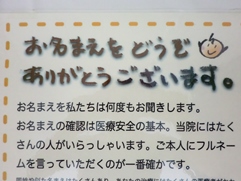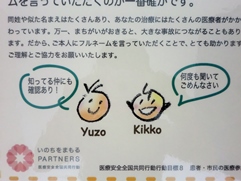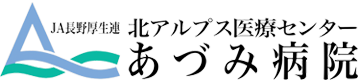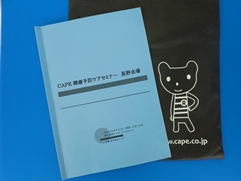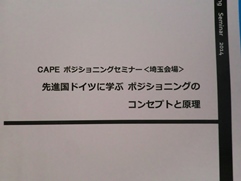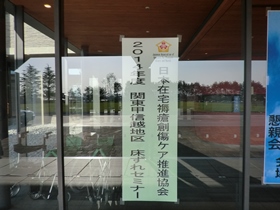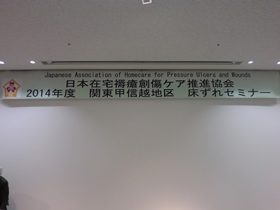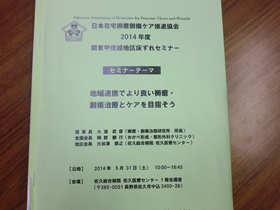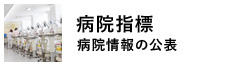WOCNブログ
ヒヤリハット劇場開幕
第22回医療安全報告会が6月20日に行われました。
今回は報告部署からの発表の前に、「ヒヤリハット劇場」があり
同姓異名患者の検査取り違えミスの要因分析を、
医療安全委員会とセーフティーマネージャー委員会のメンバーが
寸劇で発表してくれました。
1、ハインリッヒの法則総論(1:30:300の法則)
2、ハインリッヒの法則各論(1:30:300の法則)
俳優と女優になりきって!?演じていましたよ~。
寸劇も良かったのですが、ナレーションの内容がとても良く
メモが追いつかなかったので、GRMから台本を見せてもらい
ブログに書こうと思いました。
私が書き留めたかったナレーションの一部を紹介します。
「どこの病棟にも安全意識が低く、ヒューマンエラーを
犯しやすい職員が5~10.%は存在します。
フルネームで呼ぶ安全マニュアルは知っているのに遵守しないという、
困った違反行為です。どんなに優れた安全対策でも現場で
実践しなければ何の意味もありません。」
「全ての職員は患者さんでだけでなく、同僚が実施する
安全業務にも関心を高め、常に気を配る思いやりが大切です。」
「同僚によるコーチングはとても大切です。より良いチーム医療
のためには他人の業務に関心を高めることです。
医療事故は皆で防ぐ、これも大切なチーム医療です。」
「安全対策・安全業務・医療事故」
これらを「褥瘡対策」に置き換えても同じことが言えると思いました。
*病院駐車場にある桜の木ですが、一枝だけ紅葉していました。
緑と赤のコントラストが綺麗ですね。
撮影数日後には落葉してしまいました。
いつもありがとうございます。 WOCN ふりはた
WOCNブログ
美味しい学習会
6月20日に定例の褥瘡対策委員会があり、事例検討のあとに
食品メーカーの北山管理栄養士さんを講師に迎え
「栄養ケア」について学習会を行いました。
メーカー主体の学習会といっても、目的やテーマを伝え
使用する資料を見せていただき、追加や修正をお願いする必要があります。
今回は特に、創傷治癒過程と栄養素の関与や栄養素について
詳しく話していただくようお願いをしました。
北山さんありがとうございました。
褥瘡発生後の栄養療法のポイントは
亜鉛:たんぱく質、コラーゲンの合成に関与し創傷治癒には
不可欠な栄養素。皮膚の新陳代謝に作用し創傷の修復を促進する。
ビタミンC:コラーゲンの合成に関与し、不足すると皮膚の脆弱化が
起こる。加熱調理により水溶性ビタミン類は不足する。
アルギニン:たんぱく質、コラーゲンの合成を促進する作用のほか、
免疫細胞の活性化や、血管拡張による血流の改善などの作用がある。
コラーゲン:摂取によって、ヒドロキシプロリンを含むペプチドの
血中濃度が上昇することが明らかとなっている。
ペプチドは繊維芽細胞を刺激し、
皮膚の再生を促進するなど、様々な生理効果を有する。
鉄:ヘモグロビンの合成に必要であり、血清鉄が不足する赤血球数が
減少し、皮膚や軟部組織の脆弱化を招く。

(病院駐車場から虹が見えたので撮影しました。
願いが叶う場所は意外と近くにあるかも。。。)
委員会内での学習会をきっかけに、
自己学習できるとより理解が深まります。
「褥瘡患者さんのための栄養ケアポケットガイド」もいただいたので、
しっかり活用して欲しいです。
栄養機能食品の試飲や試食もできたので、
楽しく・美味しい学習会になったのではないでしょうか?
たまにはいいですね。
いつもありがとうございます。 WOCN ふりはた
WOCNブログ
おむつ学習会
7月12日と19日の2日間、整形外科病棟でおむつの学習会を行いました。
今年度固定チームナーシングの小集団活動で、
おむつに関して取り組むことを決めたチームがあり、
学習会の依頼を受けて開催の運びとなりました。
先日も他の病棟のチームから、
「アンケート調査をしたところ、スキンケアについて学習したい
という希望が多かったので、学習会をお願いしたいです。」と頼まれました。
WOC領域に関心を持ってくれただけでも嬉しいのに、
チーム活動にしてくれるなんて感激!!
全力で応援させてもらいます。(皆が引かない程度に。。。)
(ネームにコンチネンスケアのピンバッチを付けています。
緑色の物はお守りです。)
学習会の内容は。。。
コンチネンスケア・製品選択方法・アセスメント方法・
その他対応について、質疑応答を含めて45分間にまとめました。
アセスメント方法については、3択のクイズ方式を取ったので
印象に残って覚えてくれたのではないかと期待しています。
看護師の2大業務は、
「診療の補助」と「療養上の世話」ですが、
診療の補助にかかる時間の割合が多いのが現状だと思います。
「療養上の世話」に当たるのがコンチネンスケアなので、
「自分がしてもらいたいケアを患者さんに提供する」
「患者さんが幸せで、スタッフも幸せなケア」
理想とするケアの実現に向けて、一緒に頑張りたいと思っている
ことを話しました。
「絶対にできる!」とスライドにも入れたので、
きっとできるようになると信じています。


(家で見つけた四つ葉クローバーです。
スライドの写真に使用しました。
CLOVERってCとRを除くとLOVEなんですよ。)
いつもありがとうございます。 WOCN ふりはた
WOCNブログ
褥瘡予防ケアセミナーに参加しました。
6月7日体圧分散寝具メーカー主催のセミナーに参加しましたっ!
5月31日(土)6月1日(日)6月7日(土)と
短期間でセミナーが続くため心配されましたが、
以外と大丈夫!元気でした!
まぁ、最後のセミナーが安部先生ですから頑張れますわ。(楽勝?)
今回のプログラムは
第1講 いかに褥瘡を予防するか?―臨床現場における看護チームの取り組みー
松原 康美 先生
第2講 「あなたも陥る創傷ケアのピットフォール!
~53分間で学ぶ皮膚潰瘍アセスメントのコツとワザ~」
安部 正敏 先生
医療関連機器圧迫創傷とは
NPPVマスク、弾性ストッキング等の医療機器の
装着部位に生じる創傷を指し、褥瘡学会ではガイドラインの掲載に向けて
実態調査が進められています。
医療機器の種類、患者特性に応じた予防対策が必要とのこと。
手順書の作成や啓発活動については、是非参考にさせていただきたい
内容でしたが、当院はまだそこまで進んでいないのが現状です。
「これは予防できたよね」「アセスメントは良かったのに」
と言う場面も多く、ラウンドや指導が足りないと感じます。
マットレスのヘタリや、ベッドメイク時シーツの処理についても
WOCNになってからずっと指導を続けていますが、なかなか定着しません。
せっかく褥瘡予防のマットレスを使用しているのに、接触面積が減り体圧が
上昇していたら意味が無いです。
数値で示していますがなかなか。。。
少しのことで大きな違いが出ます。
徹底できるようになるまで根気良く指導すること、
良い物品を使用できるように環境を整えることが必要ですね。
また宿題が増えました。
安部先生のtake-home messagesは
1、皮膚潰瘍患者の前では、絶えず鑑別診断を念頭に置き、
誤ったアセスメントのリスクを低下させる。
2、皮膚の症状を読み取ることで、なぜその創傷が生じているのかが
理解することが出来る。
3、皮膚を正しくアセスメントすることで、手を出しては
いけない創傷の存在を知ることが出来る。
「スライドグラスをポケットに忍ばせて」
「とにかく最初は触れてみる」 (先生の資料より)
指導に追加したいと思いました。
私も含めて看護師が「アセスメント力を養う」ことが大事で、
人体最大の臓器である皮膚をよく観察し
アセスメント出来るようになると、仕事も楽しくなるんじゃないかなぁ~。
安部先生の講義は毎回新鮮で、時間がとても短く感じます。
さすがです。
「次も聞いてみたい!」と思わせることがポイントですね。
そして毎回期待を裏切らない。。。
参加者のことをとても大切に考えて下さる、
結果なのではないかと勝手に考えています。
いつもありがとうございます。 WOCN ふりはた
WOCNブログ
ポジショニングセミナーに行ってきました
6月1日さいたま市文化センターにて開催された、
セミナーに行ってきました~。
タイトルは「先進国ドイツに学ぶ ポジショニングのコンセプトと原理」
講師はザビーネ・ベッカー女史でした。
英語の講義を同時通訳で聞くといった、ちょっとおもしろい
セミナーでしたよ。(英語の学習にもなった?)
先生はドイツで看護業務に従事しながら、ポジショニングの教育を
20年来行っているそうです。
太極拳やキネステティック、コミュニケーションを基に
How toよりも原理、応用を目指して、
患者さんに活動性を提供することを、目的にされているとのこと。
原理を理解することって大事ですよね。
キネステティックには興味があって、
以前褥瘡学会のワークショップに参加したことがあります。
患者さんと介助者が協力して一緒に動くことで、介助者の腰にも優しく
安楽でリラクゼーションの効果もあるのです。
人には触られたくない面と、触られても良い面があり
(プライベートな面とパブリックな面)
柔らかい部分は触られたくない面で、硬い面は触っても良いのだそうです。
(腕だと内側はNGで外側はOK)
今まであまり考えずに触っていましたが、
嫌な思いをされていた患者さんがいたかもしれないと
思うと愕然としました。ごめんなさい。。。
ベッドの高さを調整する時も、「動きますよ」とか声を掛ければ良いと
単純に思っていましたが、“肩”や“下肢”に触れて動かした方が、
患者さんは安心するそうです。
十分だと思っていたケアがぜんぜんダメで、
患者さんに不安感を与えていたなんて。。。ショックです。。。
これらのことは簡単にできることなので、スタッフにも指導し
不安を与えないようにしようと決めました!
コミュニケーションも大事で、看護師が早い口調で強く話すと
患者さんは緊張するのでゆっくりと話すことが必要があります。
私もなるべくゆっくりと話すように心がけていますが、
患者さんの前でスタッフ指導をする時など、配慮に欠けていたと気づかされました。
「今まで何をやっていたんだろう~私」って猛省です。
知らないって怖いですね。
今までポジショニングは、意欲的なリハビリスタッフに任せきりでした。
熱心な彼らは、自主的に毎年褥瘡の研修へ参加してくれているんです。
そんなスタッフに頼ってばかりでしたが、今年はポジショニングを
もう一度しっかり勉強して、リハスタッフと連携したいと考えています。
動きの支援で呼吸や血流へのサポートにもなるので、
心不全や肺炎の患者さんへ支援できるようになると良いですね~。
「良いポジションは良いマットレスから」
「プロフェッショナルとしての用具選定」
皆でがんばりましょう!!
いつもありがとうございます。 WOCN ふりはた
WOCNブログ
関東甲信越地区床ずれセミナーに参加しました
5月31日佐久総合病院 佐久医療センターにて開催されたセミナーに参加しました。
日本褥瘡創傷ケア推進協会の第1回総会・学術集会に参加できなかったので、
「地区セミナーには絶対に行く!!」と気合を入れていましたよ。
でも気合のわりに、6月1日に埼玉でのセミナー受講が決まっていたので、
「やっぱりどうしようかなぁ~」と一瞬気持ちが揺らぎました。
プログラムがハッキリするまでは。。。。
私の迷いを解消してくれたプログラムは
教育講演1「寝床環境を整える~マットレスの適切な選定方法~」
飯田市立病院 近藤 龍雄PT
教育講演2 『ガイドブック「新床ずれケアナビ」解説』
総合希望クリニック 堀田 由浩Dr
教育講演3 『こんなにも多い亜鉛欠乏症!食欲不振、褥瘡・皮膚疾患、そして舌痛症も??
~多彩に臨床症状の謎が、最新の亜鉛研究で徐々に明らかに~』
東御市立みまき温泉診療所 倉澤 隆平Dr
教育講演4 『創に優しい体位変換の考え方~体位変換は諸刃の剣~』
褥瘡・創傷治癒研究所 大浦 武彦Dr
全国会長講演 『地域連携での褥瘡創傷治療とケア』
おかべ形成・整形外科クリニック 岡部 勝行Dr
教育講演5 『医療と介護の連携と在宅医療の推進』
佐久医療センター 小松 祐和Dr
教育講演6 『介助用リフトの急性期医療施設での運用―利用者・使用者・運用施設における効果についてー』
佐久医療センター 花沢 直樹PT でした。
豪華なプログラムでしょ?すごくないですか~
なんてったって「OHスケール」の大浦先生と堀田先生ですよ~
大浦先生がサインをして下さると聞き、並んでサインをいただきました。
ラッキー!
高名な先生方の講演は、本当に勉強になりました。
倉澤先生の資料は、写真とデータで分かりやすく講演いただきました。
大浦先生も質問されていましたが、水泡形成や浅い褥瘡に亜鉛は大変有効です。
臨床医学の専門細分化 ヒトを『人』として診る視点の欠落
『基準値=正常値』との間違ったデジタル思考
“群の基準値は個の正常値ではない”
。。。。。。。ため息がでました。
「テクノエイド」って聞きなれない言葉ですが、
福祉用具・介護機器・補助用具のことを指すそうです。
花澤さんは「テクノエイドの方がかっこいいから」って言っていましたが
それはとても大事なことだと思います。かっこいい方が断然良いです!
今年3月に開院した医療センターでは、
天井走行式リフトを入院の30%にあたる、150台導入していくそうです。
すごいですね。
安全・安心・介助者の負担軽減が(腰痛)目的ですが、
患者さんの筋緊張の低下や体重測定→スケール付きのリフト、
リラクゼーションや下肢などの、創処置にも使用できると聞きました。
心臓血管外科の術後などで、ドレーンや点滴のルートなど
たくさん装着していても、スケール付きの寝台に移乗するより安全です。
数cm体が浮けば良いのですから。
同じ長野県なのに、佐久は東京へ行くよりも大変です。
時間だって同じくらいかかります。でも頑張って行って本当に良かった!
参加できなかった人は残念でしたね~。
いつもありがとうございます。 WOCN ふりはた